50代にもなると、ライフステージが大きく変わってきます。子どもが大きくなり手間がかからなくなる一方で、寂しさや虚しさがでたり、親の介護に追われたり。ホルモンバランスが変化することもあり、体調も、家庭の状況も、突発的な「まさかの事態」が起こりやすい年代です。

「縁起でもない」と思わずに、日頃から家族のあいだで、もしもの話「もしバナ」をしっかりしておけるようになりましょう。このとき、リスクとして考えるのにいちばん抵抗が少ない、我が家の防災を考えてみることをおすすめします。
ここでは、防災を例として、「まさかの事態」にどのような向き合い方をすればいいのかをご紹介します。
このページにはこんなことが書いてあります
誰にでも関係する災害は、みんなで考える「まさかの事態」の入り口に最適
防災の話題がなぜ「もしバナ」の入り口によいかというと、災害は家族の状況にかかわらず突然やってくる外部のリスクだからです。
例えば、親の看取りやパートナーの事故などは、家族の生活状況の延長線上にあり、どうしてもそれぞれの言動や考え方との関係性を感じて「誰が悪い」という話になりがちです。
それに対して災害は、そういった人間の動きとは無関係に突然発生するため、内部の者に悪者を作らず、リスクの話がしやすいというメリットがあります。
しかも、日本は災害大国と呼ばれるくらい、毎年のように大きな自然災害が発生しています。いつどこで起こってもおかしくない災害への対処は、誰もが関係する問題として前向きに取り組みの合意がとりやすいのです。

災害にはどんな種類があるのかを知っておこう
災害は、大地の揺れや雨雲などの自然現象によって、社会に被害を与える状況を言います。
すぐに思い浮かぶのは、地震、台風、洪水、土砂災害あたりでしょうか。地域によっては、火山噴火や豪雪などの災害もあるかもしれません。このほかには、交通機関や危険物を扱う施設などによる事故災害などもあります。
このように災害は、今住んでいる地域や通勤・通学の状態などで、それぞれ影響の大きさが異なります。自分や家族が巻き込まれるとたいへんな状況になるのはどの災害かを考えて、影響の大きなものから優先的に対策を考えていくとよいでしょう。
災害が起きたらどうなるのかをイメージしておく
自分たちに大きな影響を与える災害の種類が決まってきたら、その災害が実際に自分たちの地域で起きたらどんな状態になるのかをイメージしておきましょう。
地震や風水害などに関しては、住んでいる自治体がハザードマップ(地域の危険度を地図上に表現したもの)を出しています。ハザードマップには、地域にもよりますが、おおよそ次のようなものがあります。このほか、国や自治体の防災関連のページでは、イメージしやすいよう、動画なども用意されています。
- 地震:震度分布、津波(浸水域、高さ、到達時間)、液状化、建物倒壊率、大規模火災など
- 風水害:洪水(外水・内水)、高潮、豪雪など
- その他:土砂災害(土石流、地すべり、がけ崩れ)、火山(噴石、火砕流、火山泥流)など
ハザードマップを家族で見て、自分の地域や通勤や通学経路では、どのような災害が起きやすいのか、しっかりと把握しておきましょう。
災害への対策は2つの考え方が基本となる
日本では、災害は毎年のように多かれ少なかれ起きています。地震や津波、台風を人間の力で止めることはできません。最近では異常気象で風水害などがどんどん拡大している傾向にもあります。
発生した被災状況をやりすごし、できるだけ被害につながらないようにする方法はあります。
ここでは「もしもの事態」への対策として、もっとも基本となる2つの考え方「被害抑止」と「被害軽減」について、簡単に説明します。

防災の基本は、災害が発生しても困らないようにする「被害抑止」の考え方
自然現象は抑えることができません。また、いつ起きるかもコントロールできません。このため、いつ発生しても大丈夫なように、安全や生活に被害が出ない対策を行うことが一番重要なポイントになります。これが「被害抑止」という考え方です。
聞くと当たり前に感じるかもしれませんが、命や生活基盤を失ってしまっては元も子もないですよね。例えば次のような形で、そもそも被害が起きないようにするにはどうするのがよいかを、しっかり考えましょう。
- 壁や天井の耐震補強を行う
- 重量の軽い屋根瓦に葺き替える
- 窓ガラスに飛散防止フィルムを貼る
- 大きな家具や家電、ピアノなどを金具やチェーンで固定する
- 食器棚や本棚などの中身が飛び出さないよう飛び出し防止のロック機能をつける
- 津波や風水害、土砂災害のハザードマップで我が家の避難ルートを決めておく
避けられないリスクは「被害軽減」の考え方で、少しでも減らしていこう
どんなに備えていても、大きな災害になると、どうしても被害は発生します。この場合でもすばやく対応して拡大を防ぎ、最小限の被害に抑えるのが「被害軽減」の考え方になります。
被害軽減対策の例では、次のようなものが考えられます。
- 停電に備えて大容量のバッテリーをもっておく
- ガスや水道が止まったときに備え、3日分程度の備蓄をしておく
(備蓄に関するページはこちらを参考に) - 下水管の被害に備えて簡易トイレグッズを購入しておく
- 家族の安否がわからない状態になったときのためにLINEなどでグループをつくっておく
- 災害情報アプリを入れておく
- 自治体の被災支援情報がすぐとれるよう、普段からホームページをチェックしておく
このほか、地震や浸水で壊れた家屋や家財を新調するための災害保険に入っておくなどの対策もあります。
「4つの現状」を整理して、災害へ備えよう
いざ対策をとろうと思うと、どこから手を付けたらよいかと悩んでしまうかもしれません。こんなときは、次の流れで考えを整理し、実行に移していくとよいでしょう。
- 現状把握:我が家の現在の状態がどこまで整理されているかをリストアップする
- 課題整理:災害が起きた場合にどこがいちばんのウイークポイントになるかを洗い出す
- 対策検討:現在あるものでどこまで耐えられるか、何を追加すると効果的かを検討する
- 予算実行:時間やお金の余裕を考え、何を優先させるかを決めて実行する
最初に行う「現状の整理」を行う対象として覚えておくとよいのが、「人・モノ・カネ・情報」の4つの項目です。
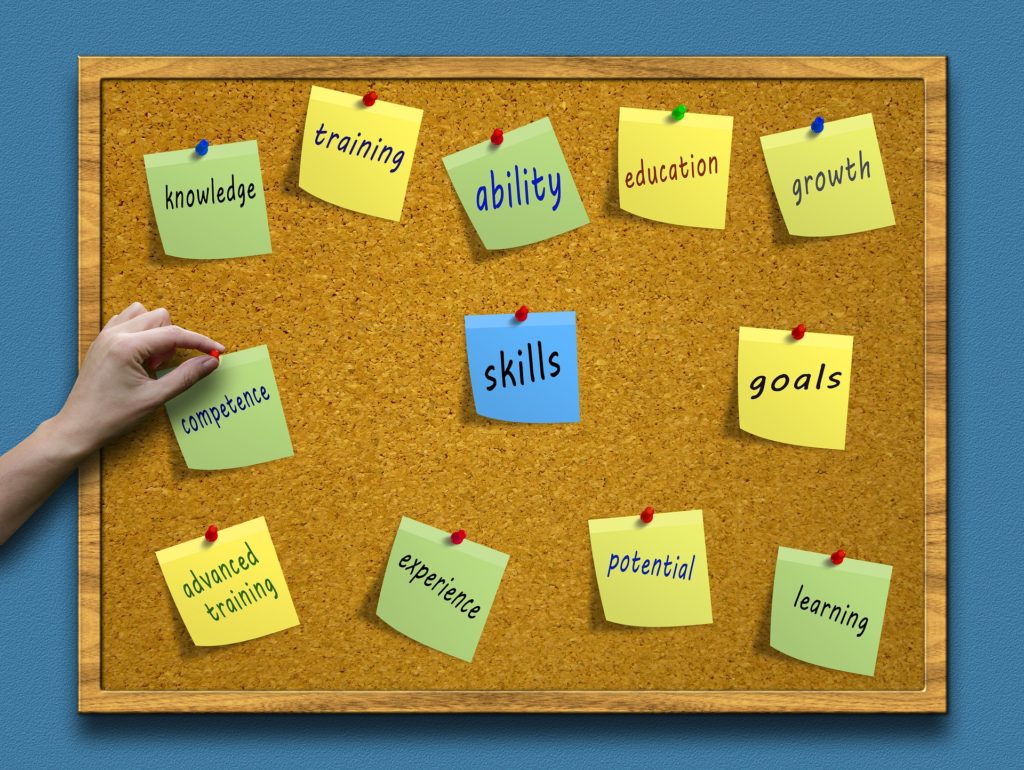
誰が、何をするか:役割分担や行動を整理する
「人」の現状整理としては、災害が発生したとき、誰がどんな行動をとるのか、協力しあうものは何か、どんな協力体制で行うか、など、非常事態に備えた役割分担や行動のフローを、簡単でよいので整理してみましょう。
また、平常時の備えについても、誰がどんな対策をとっておくのか、それぞれでやれることを洗い出すようにします。
我が家だけでは難しいものについては、親戚など頼れるところがあるのか、公的・民間サービスの利用先にはどんなものがあるのかなどもリストアップしておくとよいでしょう。
どのような資源が必要か:建物、設備、物資を整理する
「モノ」の現状整理としては、家屋の耐震やライフラインのバックアップ状況、備蓄物資など、何がどこまで整っていて、どんなものが不足しているかを整理していくイメージです。見た目でチェックできるため、リストアップしやすいことから着手しやすいものも多いのではないかと思います。(備蓄に関するページはこちらを参考に)
自治体から配布される防災関連の資料やホームページなどにチェックリストがついている場合もありますから活用してみてください。
お金(資金)はどうするか:貯蓄、収入、保険を整理する
どんな対策にもある程度のお金は必要になります。現在の貯蓄や年収、現在加入している保険などの状況を整理しておきましょう。
どのくらいまで防災にお金をかけても大丈夫かを把握し、対策を行う順序に優先度をつけて、毎年少しずつ充実させていくことで、バランスよく着実に防災力を高めていけるのです。
どうやって情報をとるか:情報の収集先や判断基準を整理する
災害発生時には電気も通信も交通もマヒするため、状況がわからず大混乱となります。
このため、命を守るにせよ、生活を回復させるにせよ、「いかに正確な情報をすばやく集めるか」が最も重要な行動となるのです。
安否の情報は家族で決めた連絡手段で、避難の情報はアプリを入れて、どの状況になったらこんなふうに行動しよう、など、集めるべき情報と情報の収集先、集めた情報で判断すべきことなどを予めリストアップしておき、ときどき使って操作に困らないようにしておきましょう。
まとめ
災害は必ずやってくると考えて、むやみに怖がらず、また根拠なく考えず、侮らず、目をそむけず、現状と対策を立てることに慣れておくことをおすすめします。要は、正しく恐れて適切に備えることが重要なのです。毎年見直して、少しずつ対策を充実させていきましょう。
災害に強い家族になると、自然災害に限らず、「まさかの事態」への対応力も十分備わっていきます。まずは取り掛かりやすい災害を入り口に、強い家族を育てていきましょう!








